高度肥満の手術:どんな治療?治療を受けるべき人は?治療内容や代替手段、リスク、合併症は?
更新日:2022/05/20
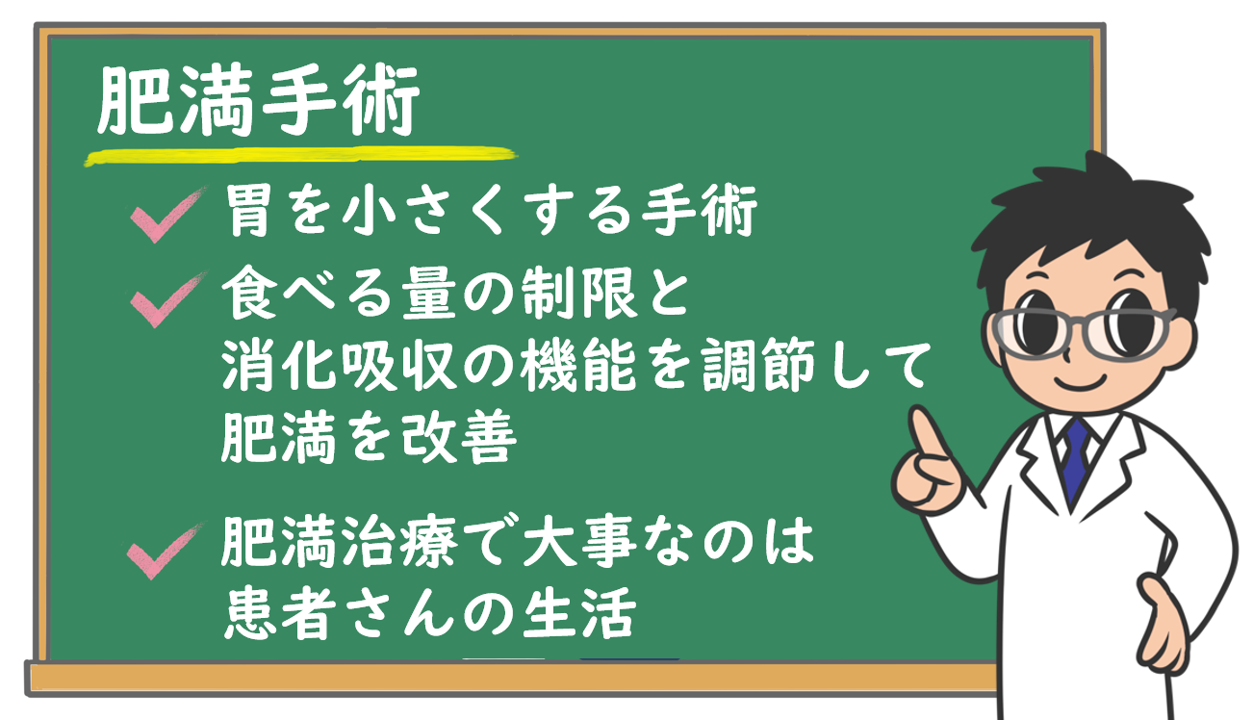 |

- 消化器外科専門医の岡住慎一と申します。
- このページに来ていただいた方は、ご自身またはご家族、お知り合いの方が高度肥満と診断され、どのような治療法があるのかについて知りたいと考えられているかもしれません。
- 高度肥満症に対する治療法のひとつである外科治療(手術)について理解するために役に立つ情報をまとめました。
- 私が日々の診察の中で、「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」、「あまり知られていないけれど本当は説明したいこと」についてまとめました。
目次
まとめ
- 肥満手術とは、手術によって胃を小さくし、食べる量を制限すると同時に消化吸収の機能を調節することで、肥満の改善を促す治療です。
- 年齢が18歳~65歳の原発性肥満症の患者さんで、6ヶ月以上の内科的治療を行っても体重減少や肥満に関わる病気の改善がみられない方に、肥満手術を行います。
- 手術後約1年で、過剰な体重が減少し、糖尿病などの病気も改善します。
- 手術の効果を維持するためには、患者さんと様々な職種によるフォローアップの連携が大切です。
どんな治療?

- 肥満の治療には、お薬などが中心の内科的治療と、手術が中心の外科的治療があります。
- ここでご説明する肥満手術とは、手術によって胃を小さくし、食べる量を制限すると同時に消化吸収の機能を調節することで、肥満の改善を促す治療です。
- 一方、内科的治療では、肥満によって起こる病気をそれぞれ治療し、食事・運動療法によって体重を減らします。
コラム:肥満とは? 肥満が招く病気とは?
- 肥満はBMI(body mass index: 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))≧25と定められています。さらにBMI≧35を高度肥満といい、高度肥満では肥満に関わる病気が増加します。
- 肥満に関わる病気には、糖尿病、高血圧、脂質異常症をはじめ、睡眠時無呼吸症候群、心臓病、腎障害、関節異常などがあります。また、悪性腫瘍や精神的トラブルも増加するとされています。
この治療の効果は?

- 肥満手術の効果は、以下の通りです。目に見える効果が、約半年から1年ででてきます。
肥満手術の効果
- 体重が約1年で20kg位減少する
- 9割の患者さんに糖尿病の改善が見られる(表1)
- インスリンやお薬がいらなくなるといった効果もしばしば見られます。
- 体重の減少にともない、運動の幅が広がり、他にも様々な肥満に関わる病気が改善します。
- 医療費、食費の減少
図表1 術式別肥満症外科治療成績
どういう人がこの治療を受けるべき?

- 肥満手術を受けられる方は、「年齢が18歳~65歳までの原発性(原因となる病気がない)肥満症の患者で、6ヶ月以上の内科的治療を行ったが、体重減少や肥満に関わる病気の改善がみられない方」とされています。(日本肥満症治療学会ガイドライン(2013))
- そのほか、肥満のために致命的な合併症がおこる可能性が高く、早く改善する必要がある人も、肥満手術を勧められます。
コラム:内科的治療で改善が見られない場合
- 内科的治療は、患者さんに食事・運動療法を厳守していただき、数ヶ月以上の治療を続けていただく必要があります。
- ただ、関節痛のために運動ができない、また、どうしても食事の量が減らせないなど、内科的治療の効果が上がらない方もおられます。
- そのような場合も、外科治療が薦められることがあります。
実際には、どんなことをするの?

- 現在の肥満手術は、ほぼ全てが腹腔鏡によって行われています。そのため、患者さんの傷の痛みや感染は減り、手術後も早く起き上がれるようになり、退院することが可能になりました。
- 日本では、以下の4種類の手術方法で、肥満手術が行われます。
1.袖状(スリーブ)胃切除術

- 袖状胃切除術とは、胃の大弯側を切り取る手術で、胃の容積を約100cc程度に小さくします。(図表2)
- 食べる量が制限されるだけでなく、食欲を起こすグレリンというホルモンが出る場所も取られるため、食欲が上がることを防ぐ効果もあります。食事が早く腸に達すると、他の消化管ホルモンにも影響し、糖尿病の改善の効果もみられます。
- 2014年から保険医療になりました。
図表2 袖状(スリーブ)胃切除術
*東邦大学佐倉病院HPより引用
2.胃バイパス術

- 胃バイパス術では、胃を切って小さくし、同時に小腸を切り、小さくした胃につなげます。反対の小腸の端は、下の小腸につなげます。(図表3)
- 食べる量を少なくする、食べ物が早く小腸へ行く、消化液(胆汁・膵液)が合流する部分をさらに下にします。その結果、体重減少と血糖の正常化が、1の袖状胃切除より効率よく進むとされています。重症の肥満・糖尿病患者に特に勧められ、欧米では主流となっています。
- ただ、欠点は胃の大半が空の状態で体に放置されることで、内視鏡検査が難しくなってしまうことです。日本では、胃癌が欧米に比べ多いので、主流ではありません。
図表3 胃バイパス術
*東邦大学佐倉病院HPより引用
3.スリーブバイパス術

- スリーブバイパス術とは、1の袖状胃切除術と2の胃バイパス術を合わせた方法です。(図表4)本邦において開発されました*
- 小さくした残りの胃が空の状態で体に放置されないので、内視鏡検査も可能です。ただ、技術的に難しく、先進医療に指定されています。
- Kasama K Obes Surg 2009:1341-5
図表4 スリーブバイパス術
*東邦大学佐倉病院HPより引用
4.胃バンディング術

- 胃バンディング術とは、胃の入口のすぐ下をバンドで狭くして食事の量を少なくする方法です。
- バンドの締め具合を調節することが可能で、内視鏡検査も可能です。ただ、袖状胃切除と異なり、胃切除をしないので、食欲亢進ホルモン(グレリン)は抑制されません。
コラム:外科手術の基本コンセプト
- 外科手術の基本コンセプトは、摂食量の調節と過剰(異常)な消化吸収状態の改善です。
- これらにより、体重減少とともに糖尿病、脂質異常を改善させるため、体重を減らす減量外科(bariatric surgery)は代謝外科(metabolic surgery)とも呼ばれています。
術式はどうやって選択されるの?

- 手術方法は、患者さんの体重、肥満に関わる病気の状態、生活環境などを総合的に評価して、最も適切な方法を選びます。生活状況、治療歴、病気の状態を、担当医とよく相談して手術方法を決めることになります。
治療を受けるにあたって

- 治療を受けるにあたって、手術はあくまでも総合的な治療の一部で、大事なのは患者さんの生活だと十分に認識することです。
- 高度肥満症は、短期間で起こる病気ではなく、長年の生活習慣をもとにしています。そのため、手術をしても生活が変わらなければ、十分な効果が得られないことや、一旦得られても元に戻る「リバウンド」という現象が生じてしまいます。
- 手術の前には、精神科医や臨床心理士の面接評価やアドバイスを受けます。一般に、手術前には約4週以上の低エネルギーの食事療法を行い、行動の評価をします。これらは、脂肪肝を小さくして手術の安全性を上げたり、フォローアップの計画に有効となったりします。
タバコを吸ってもいいの?

- 喫煙は、手術時の肺の合併症を起こしやすくします。喫煙者は1ヶ月以上の禁煙が必要です。また、禁煙できることが、手術後の効果の指標ともなります。
手術時間は?

- 袖状胃切除で約3時間、バイパス手術やスリーブバイパス手術で約5時間かかります。ただ、患者さんの体重、体格、病気の状態などにより異なります。
- 手術が終了したあとで、手術内容とかかった時間の理由などをご説明します。
麻酔について

- 全身麻酔で行います。麻酔前後に準備・処置を行うため、手術室の滞在時間は手術時間よりも1-2時間長く必要となります。
手術後の痛みについて

- 手術後の痛みについては、鎮痛剤(痛み止め)によりコントロールするので、我慢せずにお伝えください。夜は眠れるように、昼間はリハビリをできるように、痛みを抑えることは積極的に行っていきます。
理解しておきたい リスクと合併症

- 手術によって起こりうる合併症は、以下の通りです。
合併症
- 手術後の出血
- 胃や腸の縫い目から漏れ出す(縫合不全)
- 腸閉塞
- 傷口の感染
- せん妄
- ダンピング症候群
- 逆流性食道炎
- 下痢
- 貧血
- 骨粗鬆症
術後出血について

- 手術が終了する時点で止血を確認しますが、麻酔が覚めて体が動き始め、血圧が変わると再び出血することがあります。
- 少しであれば安静にして、血を止めるお薬を点滴します。血圧が下がる場合、輸血が必要なほどの貧血が生じた場合は、再び手術で血を止めることがあります。
縫合不全について

- 縫合不全とは、手術で切った胃や腸を縫い合わせた部分の付きが悪い場合、食事を再開した際漏れることです。
- 痛んだり、発熱したりしますので、一旦食事を止めて、しっかり治るまで時間をかけます。手術の後の傷の治り具合には個人差があります。
腸閉塞について

- 手術のあと、傷を治す作用と同時に、腸同士がくっつくことがあります。そうすると、腸がねじれて腸閉塞を生じ、腹痛や、食べられない危険があります。
- 手術後はベッドから早く立ち、腸同士がくっつかないようにします。
傷口の感染について

- 内視鏡で行うため傷口は小さいですが、感染する可能性はあります。
- 術前術後には抗生物質(細菌をやっつけるお薬)を使います。
- 稀に化膿した場合に、切って膿を出すこともあります。
せん妄について

- せん妄とは、手術後に麻酔薬などの手術のお薬の影響、ストレス、病室などの環境の変化によって、幻覚、不安などが生じることです。
- 心配はありません。お薬剤の選択や環境の調整などにより防止するので、生じた場合はお伝えください。一般に手術後の経過とともに消えていきます。
ダンピング症候群について

- ダンピング症候群とは、胃が小さくなり、食物が腸に早めに入りすぎると、ホルモンが過剰に反応し、胸がどきどきする(動悸)、冷や汗、めまいなどの低血糖症状が生じることです。
- 防止法は、少しずつゆっくり食事を取ることです。生じてしまった場合は、血糖値を戻すために飴などで糖分をとる必要があります。
逆流性食道炎について

- 胃を小さくするため、食後に胃内圧が上昇しやすく、また袖状胃切除では、胃酸が食道に逆流しやすくなります。逆流は胸焼けを生じ、食道に炎症が起きると、飲み込むときの痛み、ものが通りにくいなどの症状が起きます。
- この際は、お薬の治療で胃酸を調節することが必要となります。
下痢について

- 胃を小さくして、腸の中に食べ物が早く入ることにより、腸管運動が活発になり、便が何度も出たり、下痢となったりします。
- 食事の管理や、下痢止め、腸を整えるお薬を使います。
貧血について

- 胃は鉄を吸収するので、胃を小さくすることで鉄欠乏性貧血が生じやすくなります。また、赤血球をつくるのに重要なビタミンB12の吸収も抑制されます。
- 貧血が生じたら、鉄剤を飲んだり、ビタミンB12の補給をしたりすることが必要となります。そのため、術後は定期的な採血のチェックが必要です。
骨粗鬆症について

- 胃を小さくすることで、カルシウム低下が生じることがあり、骨粗鬆症の原因となる可能性があります。
- そのため、定期的に骨密度の測定や、カルシウムを摂る、ビタミンDを飲むなどの管理をします。
治療後について

- 手術後は状況により集中治療室管理とし、麻酔からの覚醒を確認し、翌日にベッドから立ち、歩行可能となります。通常、術後3日~7日で退院可能となります
- また、フォローアップが重要で、手術の成功を左右すると言っても過言ではありません。体重、肥満に関わる病気、合併症についてフォローしていくことが重要です。原則として、術後1年までは1~3ヶ月ごと、2年目からは6~12ヶ月ごと受診して、減量、肥満に関わる病気の改善、栄養管理およびリバウンド防止を行います。
- これらは、外科医のみならず、多職種によるチームの連携により行っていきます。具体的には、定期的な採血で、栄養状態、代謝の病気がないかチェックし、不足があれば補充します。
ガイドラインなど追加の情報を手に入れるには?

- より詳しい情報や最新の知見などについては、以下のウェブサイトを参照して下さい。
- 日本肥満症治療学会ウェブサイト
- http://plaza.umin.ne.jp/~jsto/



