食中毒・食あたり:原因は?潜伏期間は?人にうつるの?治療は?
更新日:2020/11/11
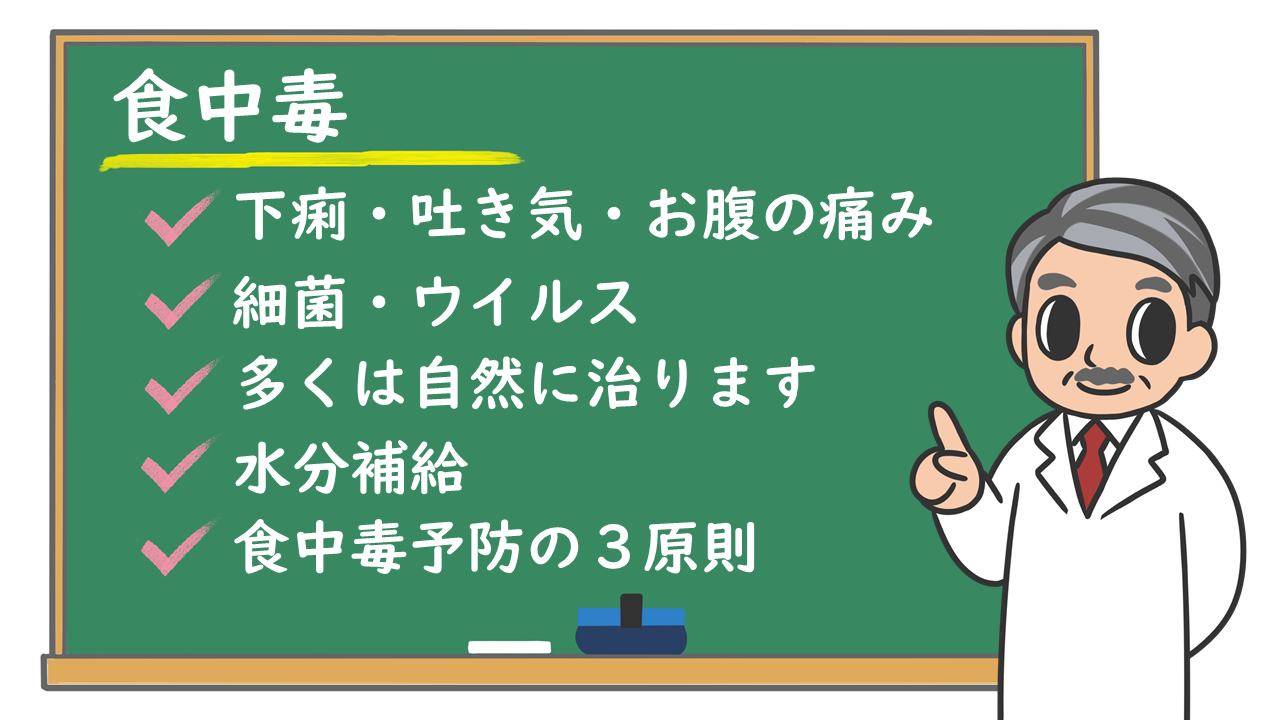 |

- 消化器内科専門医の秋穂 裕唯と申します。
- とつぜんお腹が痛くなったり、ひどい下痢が何日も続いたりすると、心配になりますよね。何か悪い原因で起こっているのではないか?と心配されたり、「病院に行ったほうが良いかな?」と不安になられたりするかもしれません。
- そこでこのページでは、食中毒 の一般的な原因や、ご自身での適切な対処方法、医療機関を受診する際の目安などについて役に立つ情報をまとめました。
- 私が日々の診察の中で、「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」、「本当に知ってほしい」けど本当は説明したいことについて記載をさせていただいています。
目次
まとめ
- 食中毒とは、微生物(細菌、ウイルス)、毒キノコなどの自然毒、農薬などの化学物質などがついた食品を食べることによって、下痢、おなかの痛み、熱、吐き気などの症状が出ることをいいます。
- 1日10回以上の下痢があったり、血が混じっていたり、強いはき気やおなかの痛み、熱、頭の痛みなどがあれば、近くの病院を受診してください。
- 何度も吐き、途中から血も一緒に出てくる場合、おう吐や下痢がひどくて水を飲めていない場合、フグやキノコを食べた後に、しびれ、息がしづらいといった症状がある場合はすぐに救急車を呼んでください。
- 食中毒の症状はつらいですが、一般的には自然に治ることが多いです。病院での治療は、輸液、食事、お薬の治療を行います。
- 食中毒を予防することも大事です。細菌を「付けない」「増やさない」「やっつける」の3原則を覚えておくとよいでしょう。
食中毒とは?

- 食中毒とは、微生物(細菌、ウイルス)、毒キノコなどの自然毒、農薬などの化学物質などがついた食品を食べることによって、下痢、おなかの痛み、熱、吐き気などの症状が出ることをいいます。
- 同じ食べ物で複数の人が食中毒になることを集団食中毒といいます。食中毒の患者さんを診断した医師は24時間以内に保健所に届け出なければいけません。
どんな症状?

- 主な症状は、以下の通りです。とくにお年寄りの方やお子さんは、重症になりやすいので、特に注意が必要です。
食中毒の症状
- 下痢
- おなかの痛み
- 熱
- 吐き気、吐く
- 脱水:下痢や吐く症状がひどくて水分をとれていないと起こります。
特徴的な症状がでる食中毒

- 腸管出血性大腸菌:「O-157」で知られています。血便、尿毒症、脳症になることがあります。
- フグ毒:口や手指のしびれから始まり、息ができなくなることがあります。
- 毒キノコ:神経が麻痺し、命にかかわることがあります。
こんな症状があったら救急車を!

- 最近(ここ1週間で)、食中毒になる可能性がある食品を食べたかどうか思い出してください。
- 何度も吐き、途中から血も一緒に出てくる場合は、食道が裂けているかもしれません。すぐに検査をして治療する必要があります。
- おう吐や下痢がひどくて水を飲めていない場合は、ひどい脱水になっている可能性があります。
- フグやキノコを食べた後に、しびれ、息がしづらいといった症状がある場合は、命にかかわることがあります。救急車を呼んですぐに病院へ行ってください。
こんな症状があったらかかりつけ医を受診してください

- 1日10回以上の下痢があったり、お尻から血がでたり、強いはき気やおなかの痛み、熱、頭の痛みなどがあれば、近くの内科・胃腸科の病院を受診してください。
- 食中毒になりそうな食品を食べていなくても、目に見えない化学物質が混入していたり、まわりの人からうつされた場合もあります。
主な原因とその説明

- 食中毒の原因のほとんどは細菌とウイルスです。細菌は高温多湿を好むので、夏に細菌性食中毒が多くみられます。ノロウイルスなどのウイルス性食中毒は感染力が高く冬に多くみられます。
- 他には真菌(カビ)によるものやフグや毒キノコなどの自然毒、農薬やヒ素などの化学物質などが原因になります。肉や赤身魚のヒスタミンによるアレルギー様食中毒もあります。
コラム:食中毒の患者数の統計
- 厚生労働省の統計では、食中毒の患者数はノロウイルスが最も多く、死者は腸管出血性大腸炎とサルモネラが多くなっています。
- 十分に加熱していない卵、肉、魚などが、食中毒の原因になっています。
細菌性食中毒

- 細菌性食中毒は発症機序により毒素型と感染型に分類されます。
- 毒素型は、生体外で産生された毒素が原因となる食中毒です。潜伏期間が非常に短く、黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌などがあります。
- 感染型には生体内で毒素が産生される腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオなどがあります。毒素が産生されない細菌にはサルモネラ菌、カンピロバクター菌、病原性大腸菌などがあります。
ウイルス性食中毒

- ウイルス性食中毒では、十分に加熱していない生ガキを食べたことによるノロウイルスが多くみられます。感染力が非常に強く、ヒトからヒトへの感染の方が食品を介する食中毒より多くみられます。
- 他に食肉からのE型肝炎ウイルスや、アサリなど二枚貝からのA型肝炎ウイルスなどがあります。
寄生虫による食中毒

- 寄生虫では、サバやイカに寄生するアニサキスや、ヒラメに寄生するクドアなどが食中毒の原因となります。
自然毒による食中毒

- 自然毒による動物性食中毒では、強力な神経毒で呼吸困難になるテトロドトキシンによるフグ毒が多くみられます。
- 毒キノコなどの植物性自然毒には、胃腸障害を来すカキシメジ、クサウラベニタケなどがあります。タマゴテングダケやドクツルタケは命にかかわることがあります。
コラム:食中毒の原因の細菌やウイルスの潜伏期間
- 黄色ブドウ球菌:30分~6時間
- 腸炎ビブリオ: 4~96時間
- 腸管出血性大腸菌: 12~60時間
- サルモネラ菌: 6~48時間
- カンピロバクター:2~7日
- ノロウイルス: 1~2日
食中毒の原因となる食べ物は?

- 食中毒の代表的な細菌とウイルス、原因となる食べ物を、以下にまとめました。
食中毒になる可能性がある食べ物
- 黄色ブドウ球菌:汚染された手で作られたおにぎり
- 腸炎ビブリオ:生の魚や貝
- 腸管出血性大腸菌:加熱が不十分な肉、水、生野菜
- サルモネラ菌:加熱が不十分な卵・肉・魚
- カンピロバクター:加熱が不十分な鶏肉、水、生野菜
- ノロウイルス:加熱が不十分な二枚貝(カキ、アサリ)、水
こんな症状があったら救急車を!

- 最近(ここ1週間で)、食中毒になる可能性がある食品を食べたかどうか思い出してください。
- 何度も吐き、途中から血も一緒に出てくる場合は、食道が裂けているかもしれません。すぐに検査をして治療する必要があります。
- おう吐や下痢がひどくて水を飲めていない場合は、ひどい脱水になっている可能性があります。
- フグやキノコを食べた後に、しびれ、息がしづらいといった症状がある場合は、命にかかわることがあります。救急車を呼んですぐに病院へ行ってください。
食中毒に対して、よくなるために自分でできることは?

- 食中毒でつらい症状があるときにご自身でできることを下記にまとめました。
水分をとる

- 症状が軽い場合は、水分をよくとっていただき、脱水にならないようにしてください。下痢や吐くことで体の水分やミネラルが失われます。
- 水よりは、できればスポーツドリンクの方がよいでしょう。
横向きに寝る

- たくさん吐いてしまっている場合は吐きやすい体勢で横になってください。あお向けで寝ると、吐いたものがのどに詰まってしまうことがあります。
- 高齢の方や小さい子どもの場合は、口の中に吐いたものが残らないようにビニール手袋をしてかき出してあげてください。
おなかにやさしいものを食べる

- 食欲があれば、おかゆやうどんなど、おなかにやさしいものを食べてください。
下痢止めは飲まない

- 下痢がずっと続くのはつらいですが、食中毒の原因が出ていかないと症状が長引くので、下痢止めは飲まないようにしてください。
便や吐いたものをきちんと処理する

- 床などに飛び散った便や吐いたものは、使い捨てのマスク、エプロン、ビニール手袋を着けてふき取り、ビニール袋に密封して捨ててください。
- 汚れた場所とそのまわりを、次亜塩素酸ナトリウムで消毒してください。
- 処理中とその後はしっかり換気してください。
お医者さんでおこなわれること

- まずは問診で次のようなことを伺います。受診される前にメモなどにまとめていただけると役立ちます。
ご質問内容
- 症状が出る前、何を食べたか。
- 同じ食事をとった人に同じような症状が出ているか。
- ペットを飼っているか。最近動物にさわる機会があったか。
- 最近どこか旅行に行っていたか。
- 熱はあるか。
- 吐いた回数、量は。
- おしっこは出ているか。
- 便は1日何回出るか。量、色、硬さはどうか。血が混じっていないか。

- 次に全身の状態をみます。おなかを触ったり、血圧を測ったりします。
- そのあとは検査にうつります。血液、おしっこ、便の検査をして、菌や毒がないか確認します。必要であれば画像検査をして、おなかの状態やリンパ節が腫れていないかをみます。
食中毒を予防するにはどうしたらよいの?

- 食中毒の予防に大切な原則を3つ、下記にまとめました。
食中毒予防の3原則
- 付けない!:手をよく洗い、新鮮で適切に管理された食材を、清潔に調理してください。
- 増やさない!:冷蔵や冷凍を利用して、ばい菌の増殖を防いでください。
- やっつける!:中心部まで十分に加熱することで、大部分の食中毒は予防できます。調理後は2時間以内に食べるとよいでしょう。ただし、ブドウ球菌の毒素、フグ、キノコなど自然毒の大部分は、加熱しても効き目がありません。
病院ではどんな治療をする?

- 食中毒の症状はつらいですが、一般的には自然に治ることが多いです。病院で行う治療は輸液、対症療法になります。
輸液

- 脱水している場合は点滴で輸液を行い、水分を補います。
対症療法

- 対症薬物療法として、お腹の調子を整える整腸剤や、善玉菌のプロバイオティクスを投与します。
- 腸管内容物の停滞時間を延長し毒素の吸収を助長する可能性がある止瀉薬や鎮痙剤は避けるほうが望ましいです。
- 患者さんの状態によっては、抗菌薬も投与します。適応となる細菌はサルモネラ、カンピロバクター、エルシニア、腸管出血性大腸菌、C difficileなどです。
- ボツリヌスには抗菌薬は効きません。抗毒素血清を投与し、適切な人工呼吸管理が必要になります。
- フグ毒では経過観察入院となります。神経症状がある場合は、人工呼吸管理を準備します。
- キノコ中毒では、キノコを吐かせ、必要に応じて胃洗浄、吸着剤などの処置を行います。
コラム:抗菌薬の使用について
- 初診時には食中毒の原因菌がわからないため、ニューキノロン系抗菌薬かホスホマイシンを3-5日投与します。小児にはホスホマイシンを投与します。カンピロバクターにはマクロライドが有効です。
- 抗菌薬投与前に必ず便培養を行い、結果を見て抗菌薬の変更または中止を行います。
ガイドラインなど追加の情報を手に入れるには?

- より詳しい情報や最新のガイドラインなどについては以下の書籍やウェブサイトを参照してください。
- 「感染性腸炎A to Z」第2版 大川清孝ほか 2012年 医学書院
- 食中毒統計調査 厚生労働省
- http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/112-1.html
- JAID/JSC 感染症治療ガイドライン 2015 ―腸管感染症―
- www.chemotherapy.or.jp/guideline/jaidjsc-kansenshochiryo_choukan.pdf



