冠動脈バイパス術:どんな治療?入院期間はどれくらい?安全性や再発は?
更新日:2020/11/11
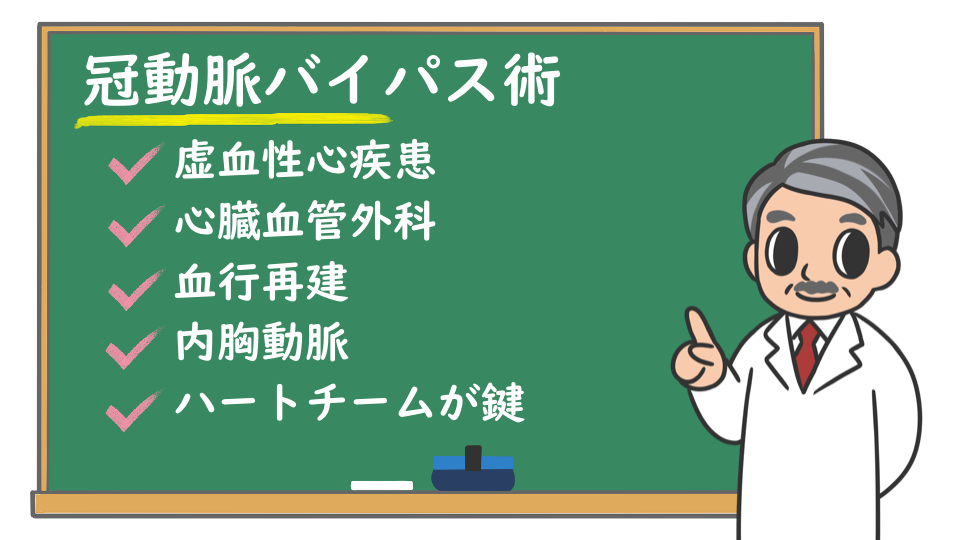 |

- 循環器専門医の中川 義久と申します。
- このページに来ていただいた方は、狭心症や心筋梗塞などの心臓の病気があり、冠動脈バイパス術(CABG)による治療を医師から薦められているかもしれません。心臓の手術を受けることには不安を感じることでしょう。
- 心臓の治療法は1つだけでなく複数の手段があります。適切に治療方法を選択するために役に立つ情報をまとめました。
- 私が日々の診察の中で、「よく質問を受けること」、「日常生活での注意」などについても記載をさせていただいています。
目次
まとめ
- 冠動脈バイパス術(CABG)とは、心臓の筋肉(心筋といいます)に血液を送る冠動脈が、狭くなったり閉塞したりすることに対する治療の手術です。
- 手術の目的は、心筋に血液が十分供給されるように治すことです。詰まった冠動脈の先に迂回路(バイパス)をつくる、血行再建法という手術の1つです。
どんな治療?

- 冠動脈バイパス術について説明するために、まず、心臓と心臓の病気について簡単にお話しさせてください。
- 心臓の筋肉である心筋は、冠動脈という血管から血液と酸素を送られています。冠動脈は、右に1本と左に大きく分かれた2本があり、全部で3本あります。狭心症や心筋梗塞などの病気は、この冠動脈が狭くなったり詰まったりすることによっておこります。
- 治療法として大切なのは、心筋に血液が十分に送られるように、詰まっている血管を直すことです。これを血行再建といいます。
- 血行再建の方法には、冠動脈形成術(PCI)と呼ばれるカテーテルを用いた血管内治療と、冠動脈バイパス術(CABG)の2つがあります。
- ここでご説明する冠動脈バイパス術は、狭窄した冠動脈の先に別の血管を縫いつけて、迂回路(バイパス)を作る手術です。
- 循環器内科医と心臓血管外科医が協力し、冠動脈の状態や患者さんの状態に合わせて最適な治療法をご提案します。
この治療の目的や効果は?

- 冠動脈バイパス術の目的は、冠動脈を詰まらせて狭心症や心筋梗塞の原因となっている病変の先にバイパスを作り、心筋へ送られる血流を増加させることです。
- 冠動脈が詰まっていたため血液が不足していた心筋に豊富な血液が送られるようになり、胸の痛みなどの症状が改善されます。
- また、心臓の機能が回復して、寿命を延ばすことができます。
どういう人がこの治療を受けるべき?

- 3本ある冠動脈のうち、2本以上の冠動脈が悪い場合や冠動脈の動脈硬化が進んだ患者さんでは冠動脈バイパス術が多く選択されます。
- とくに糖尿病を合併している場合には、冠動脈バイパス術のほうが長期的には予後が良いとする報告が多くあります。
- また、重症度の低い冠動脈が1本だけ悪い場合には、カテーテルを用いた冠動脈形成術を行うことが一般的です。
- ただし、冠動脈形成術と冠動脈バイパス術のどちらを選ぶかは、専門医の間でも議論が続いています。患者さんの状況に応じて最適な選択を行えるよう、主治医の先生とよくご相談ください。
コラム:冠動脈バイパスの選択の詳細
- 施術をうける患者さんの負担はPCIの方が低く、カテーテル治療の技術・器具の進歩に伴い、従来は冠動脈バイパス術が施行された症例でも、PCIが選択される場合もあります。
- PCIによるカテーテル治療では冠動脈の血行再建を行うのみですが、弁膜症や心室瘤など心臓外科手術での修復も必要な病態の合併例では、同時に冠動脈バイパス手術が選択される場合もあります。
- PCIと冠動脈バイパス術の治療方針の選択については、地域での医療体制、術者の技量や施設の状況なども考慮しなければなりません。
実際には、どんなことをするの?

- 狭窄したり詰まったりした部位の迂回路(バイパス)を作るため、冠動脈に身体の別の部分から取り出した血管を針と糸を使って縫い合わせます。(図1)
- バイパスに使う血管には、足の静脈(大伏在静脈)や胸の中の血管(内胸動脈)、手首の血管(橈骨動脈)、胃の血管(胃大網動脈)などが選ばれます(図1)。
- 冠動脈バイパス術を行うときは、全身麻酔をかけます。また、患者さんの心臓をいったん停止させて、人工心肺という装置を心臓の代わりにして行うオンポンプ手術と、心臓を動かしたまま行うオフポンプ手術があります。
- どちらの方法にもメリットとリスクがあるため、患者さんの病態や年齢、健康状態などを総合的に判断して決定します。
図表1 冠動脈バイパス術イメージ
他にどのような治療があるの?

- 冠動脈の詰まりを治療する方法には、冠動脈バイパス術のほかに、薬物療法や冠動脈形成術があります。
薬物療法

- 冠動脈の狭窄の程度が軽い場合には、冠動脈バイパス術や冠動脈形成術などの手術を行わず、薬剤による治療で様子をみる場合もあります。
冠動脈形成術(PCI)

- 冠動脈の詰まっている部分に、金属製の筒形の器具(ステントと言います)を入れて、血管を内側から広げる治療です。
- 血管が再び詰まることを予防するお薬を含むステントが登場し、PCIの治療成績は向上しています。
- PCIと冠動脈バイパス術のどちらを選択するかは、専門医でも判断に苦慮する場合があります。担当の先生と十分にご相談いただき、方針を立ててください。
理解しておきたい リスクと合併症

- 全身麻酔下で行う手術ですので、慎重に準備し対応しても次のような合併症がおこる場合があります。
合併症とリスク
- 術後出血:冠動脈バイパスを縫い付けたところ、あるいはバイパス用の血管を採取したところから、手術後に出血することがあります。もう一度手術室に移動していただき、出血を止める手術を必要とする場合もあります。
- 脳梗塞:上行大動脈という血管が厚くなっていたり、石のように固くなっていた場合、手術を行うことで詰まっていた血管のかけらが脳に移動し、脳梗塞の原因となる場合があります。
- 腎不全:手術前から腎機能障害がある患者さんは、悪化することがあります。
- 術後感染症:手術の傷で免疫力が低下し、約1%の患者さんで手術後に感染症がおこるとされています。
治療後について

- 手術の翌日にはベッドを起こして座り、普通の食事を始めます。
- 個々の患者さんの術前の状態や心機能で異なりますが、3日目位からご自分で立ってトイレへ行くことができるようになります。
- 多くの場合、大体2週間以内には退院されます。
ハートチームの重要性

- 近年、心臓病に関わる領域で、ハートチーム (Heart Team)という言葉がよく使われます。これは最初に、「ヨーロッパ心臓病学会」と「ヨーロッパ心臓外科学会」が共同で提唱したものです。
- 冠動脈バイパス術(CABG)とカテーテル治療(PCI)の選択においては、循環器内科医のみや心臓血管外科医のみの単科医師が治療方針を決めるのではなく、共同で最適な判断をすべきとされています。なぜなら、冠動脈疾患は、動脈硬化や糖尿病といった全身疾患を背景としています。心臓のみを治療しても完治したことにはならないのです。
- 患者さんに合理的かつ総合的な医療を受けて頂くためには、ハートチームよる取り組みが必須となります。ハートチームには、循環器内科医や心臓血管外科医だけでなく、麻酔科医、臨床工学技士、放射線技師、看護師なども包括されます。そのようなハートチームとして包括的なチーム医療を提供してくれる医療施設を選択することが大切です。
冠動脈バイパス術を受けても、今まで通り仕事や運動などの生活ができますか?

- 「退院後も動かずに安静にしていなさい」と言うのが普通だった時代もありますが、冠動脈バイパス術を受けた方には退院後、むしろ積極的に運動してもらっています。
- 現在は、適切な運動を続けることで病気の再発を予防する心臓リハビリテーションが注目されています。適切な運動を続けると高血圧、高血糖、脂質異常など動脈硬化の要因が改善して再発や死亡が減少し、体力と生活の質の向上も期待できます。心臓病だからこそ運動が必要という考え方に変わってきているのです。
- また、お仕事の内容にもよりますが、多くの方が以前と同じ仕事に復帰しています。ただ、過度のストレスは心臓病を悪化させます。仕事のストレスを完全になくすことは難しいですが、ストレスは適宜発散して心穏やかに生活するように心がけてください。運動もストレスの解消に有効です。
ガイドラインなど追加の情報を手に入れるには?

- ⽇本循環器学会ガイドライン「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018年改訂版)」
- https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2018_nakamura_yaku.pdf



