肝生検:何がわかるの?どんな時に必要なの?痛みはないの?安全性は?
更新日:2020/11/11
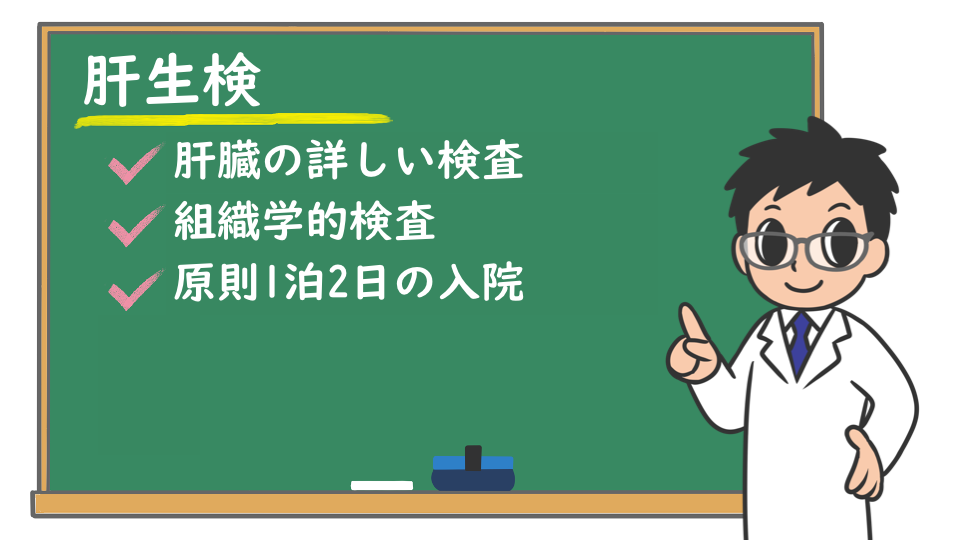 |

- 消化器病専門医、肝臓専門医の畑中健と申します。
- このページをご覧になった方は、肝疾患についてどのような検査があるのかについて知りたいと考えられているかもしれません。
- 肝生検について理解する上で役に立つ情報をまとめました。
- 私が日々の診察の中で、「特に注意をしてほしいこと」「よく質問を受けること」「本当に知ってほしいこと」について記載しております。
目次
まとめ
- 肝生検は、肝腫瘍を含む様々な肝臓疾患の原因や病態を、詳しく調べるために行います。
- 超音波で肝臓の位置を確認し、細い専用の針を刺して、肝臓のごく一部を採取して、顕微鏡で詳細に検査を行います。
- 1泊2日の入院で行い、検査時間はおよそ30分から1時間程度で行います。
どんな検査?

- 肝生検は、画像診断で見つかった肝腫瘍を含む様々な肝臓疾患の原因や病態を診断するために行います。
- 超音波で肝臓の位置を確認し、専用の針を刺して、肝臓のごく一部を採取します。そして、採取したものから標本を作製して、顕微鏡で診ることで詳しく調べる検査です(組織学的診断といいます)。
- 血液検査や画像診断ではわからない肝臓の詳しい情報が得られる可能性があります。
- 肝生検は原則として、1泊2日の入院で行います。
実際には、どんなことをするの?

- 肝生検で実際に行われることを下記にまとめました。
検査前

- 血を固まりにくくする薬や血をさらさらにする薬(抗血小板薬や抗凝固薬)は、出血しやすくなるため、あらかじめ中止する必要があります。
検査の手順

- 検査をするときは、患者はあおむけの状態で行います。右手は後頭部に置いてください。
- 検査中は、危険ですので大きく動かないでください。
- 肝臓があるお腹の右上の部分(右上腹部)を中心に消毒をします。
- 超音波で肝臓の位置を確認します。その後、皮膚と肝臓表面に局所麻酔を行います。
- 中空の細い専用の針を目的の肝臓内まで刺して、肝臓のごく一部を採取します。
検査にかかる時間は?痛みはある?

- 肝生検は、基本的に1泊2日の入院で行います。検査時間はおよそ30分程度ですが、それ以上長くなることもあります。
- 針を刺す予定の皮膚と肝臓の表面に局所麻酔を行います。この時に痛みを感じることがあります。また、麻酔をしたとしても、針を刺した部位、肩、みぞおちに痛みを感じることはあります。
- 緊張や苦痛を和らげるために、鎮痛剤や鎮静剤を筋肉に注射する、または点滴から注射することがあります。このときの注射も痛みが伴うことがあります。
他にどのような検査法があるの?

- 肝生検の代わりの検査として、血液検査や、超音波検査、CT検査、MRI検査などが考えられます。
- これらの検査の最大のメリットは、入院を必要とせず、痛みを伴わずに外来で行えます。
- しかし、病状によっては、肝生検を行わないと、確定診断ができなかったり、治療方針が決められないことがあります。
理解しておきたいリスクと合併症
出血

- 胸やお腹の壁を傷つけたり、肝臓内の血管を傷つけることにより、まれに出血することがあります。
- お腹の中や胸の中、肝臓表面、胆道に出血します。安静によって自然に止血することが多いのですが、止血しない場合は輸血や緊急で処置や手術が必要になることがあります。
肝臓周囲の臓器損傷

- 検査によって肝臓の周りの臓器を傷つけることがあります。
- 例えば、肺を傷つければ気胸が起きます。
- 腎臓を傷つければ腎損傷による血尿が起きることがあります。
薬剤アレルギー

- 緊張や苦痛を和らげるために使用した鎮静剤や鎮痛剤、痛みを抑えるために使用した局所麻酔剤などで、まれに発疹や気持ち悪さなどのアレルギー症状が起きることがあります。
- ごくまれにですが、血圧が低下するなどの重篤な症状を起こすことがあります。
肝播種【かんはしゅ】

- 肝臓の悪性腫瘍を生検する場合、まれにですが、専用の針を入れた肝臓の経路または刺したお腹の膜に癌細胞が付着して、数か月から数年後に癌病変が出現することがあります。
その他

- 上記以外にも、まれな予期できない合併症が起こることがあります。
検査後の注意は?

- 肝生検後はベットの上で、数時間安静となります。
検査後にこんな症状があったらスタッフに伝えてください

- 肝生検後に注意すべきことを下記にまとめました。これらの症状があらわれたら、医療スタッフに伝えてください。
肝生検後に注意すべきこと
- 出血:お腹が痛い、刺した皮膚が腫れてきた、など
- 薬剤アレルギー:皮膚に発疹ができた、かゆくなった、めまいがする、息苦しいなど

- 上記以外にも気になる症状がありましたら、気軽に周りのスタッフに相談してください。


